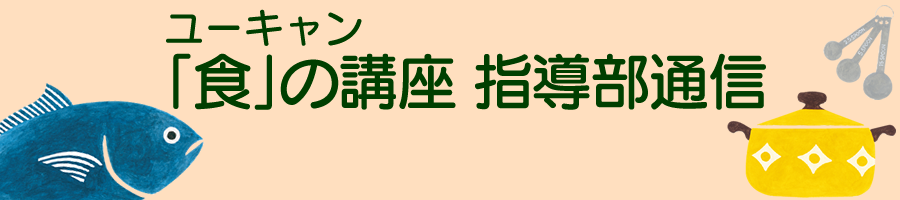2025年3月19日 農業の新潮流「リジェネラティブ」って何?

卒業入学、就職や転勤と何かと忙しい時期ですが、同時に各地それぞれに桜をはじめとしたお花見の季節でもあります。街路樹や公園、花壇などに咲く鑑賞用の花々は美しく目を奪われますが、見て美しいだけではない、別の役割を持った花があるのはご存じですか?例えば、畑や田んぼ一面に咲く、レンゲや菜の花、ひまわりなどは「緑肥」と呼ばれ、花が咲いた後に根と茎葉を刈り取って土壌にすき込むことで、土壌の保水性や透水性を改善したり、病害虫や雑草を抑制したりする目的で植えられ、農家の皆さんは花を愛でるのではなく肥料としての役割で栽培されているそうです。このように、近年、化学肥料や農薬などを減らすだけでなく、土の力を最大限に活かす、いわゆるサステナブル(持続可能な)農法が模索されています。そこで今回は、5年10年先の食料事情に大きな影響を与える、農業の近未来についてお話してみましょう。

その前に基礎として、野菜売り場などでよく目にする「有機栽培(有機JAS)」と「自然栽培」の違いは分かりますか?「有機栽培」と「自然栽培」は、どちらも環境に配慮した持続可能な農業のことですが、使用する資材や栽培方法に違いがあります。
有機栽培では、天然由来の農薬や有機肥料(植物性・動物性)を使い、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しません。農林水産省の有機JAS認証制度があり、費用が掛かりますが公的な保証が受けられ「有機JAS」を表記できるなどの利点があります。対して、自然栽培は「圃場(農産物を育てる場所)の外からは何も持ち込まない」が原則なので、肥料も入れないし、もちろん農薬は使用しない農法です。生育を自然のサイクルに任せるため、土壌の微生物や植物の相互作用を大切にし、循環を尊重した栽培が行われ、特にうま味を強めたり形を整えたりせず、植物の持つ個性そのままの風味が重視されます。

▲リジェネラティブ農法の農産物を使用したランチプレート
近年、上記の農法とは根本的に違う「リジェネラティブ農法」という農法が注目を集め始めています。この農法の特徴は、農地や自然環境の健康を回復し、持続可能性を高めることを目的とし、従来の農法では土壌の劣化や生態系の破壊が問題になりますが、リジェネラティブ農法はその逆で、土壌や環境を「再生」させながら作物を育てるという新しいアプローチを取ります!
具体的には①有機物(植物の根の破片、剥脱した根細胞、根からの分泌物、落葉、枯れた植物体の小片、家畜の排泄物、微生物の細胞、腐植物質)を増やし、土壌の栄養素を保って土壌の健康を回復させ、土壌に炭素を吸収させることで、気候変動の緩和に貢献する、②単一作物の栽培を避け、一つの畑で多様な作物や植物を育てることで連作障害を防ぐ、③化学肥料や農薬を削減して環境負荷を低減する、④土を耕さないことで、土壌の層が自然のまま維持され、微生物や有益な生態系が破壊されにくくなるだけでなく、農家の労力も軽減される。

▲リジェネラティブ農法の農産物
何となく想像できますか?耕されていない地面に、野菜やハーブ、花、雑草などが雑然と栽培され、土の中にはミミズや菌類が生き生きと活動して栄養素を送り、できたものから収穫して、常に何かが植えられ何かが育っている畑です。最終的に動植物と人間の持続可能な生態系を作る=共存を重視する農法なので。
リジェネラティブ農法は、地球環境に配慮した生産方法として、特に気候変動や食料安全保障が課題となる現代、欧米では7~8年前から重要視されていて、やっと日本でも北海道を中心として取り組む農家が出てきている現状です。近未来の食を考える際、間違いなくキーワードとなってきますので、この機会にぜひ覚えておいてくださいね。
ユーキャンでは、食に関するさまざまな講座をご用意しています。
ご興味のある方はぜひこちらから→「ユーキャン食関連講座のご案内」