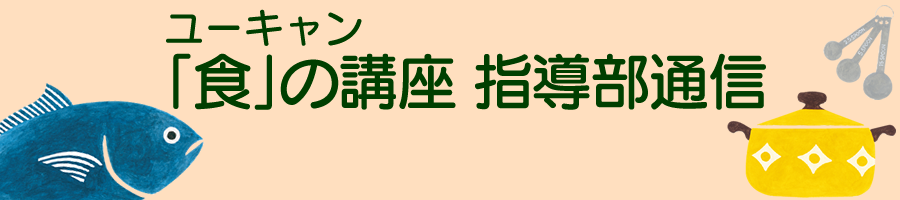2025年2月10日 汁だくのごった煮鍋VSプロの鍋料理 ~違いは何?~

今年の冬は暖冬傾向とは言え、空気が乾燥する季節ですから、やはり食べたくなるのは、お汁がおいしい熱々の鍋物ですよね。一言に鍋料理といっても世界中にはありとあらゆる鍋料理がありますが、今回は特に、日本全国に広がる和風鍋に絞ってお話していきましょう。

基本的に日本の鍋料理は郷土料理がベースにあるのですが、その歴史は思いのほか古く、起源は縄文時代の土器を用いた調理法が始まりとされています。当時は手に入った食材を土器に入れて煮る方法が主流で、現在のような寄せ鍋スタイルが確立されたのは江戸時代から明治時代とされています。それまでの日本の食事は、各人が四角形のお膳の前に並んで、もしくは向かい合って座り、一人分ずつ盛られた料理を各々が食べる形式だったのですが、主に長崎地方で「卓袱(しっぽく)」という料理が登場し、大きな器に料理を盛り付けて食卓の中央に置き、"皆で取り分けるスタイル"が広まりました。また、持ち運び可能な七輪の普及により"煮込みながら食べるスタイル"が広まったとも言われており、地域ごとに特色ある具材や出汁を使い、今日まで様々なバリエーションが楽しまれるようになりました。そもそも、日本の鍋料理のほとんどはいわゆる寄せ鍋で、基本の出汁に加える具材の種類で鍋のネーミングが決まります。全国津々浦々まで広まったその魅力は、豊富な具材と多様な味付けにあり、好みの食材を取り合わせて煮ることで美味しく調理できる点が多くの人に愛されている要因と言えます。今日では、豊富な種類の鍋汁が市販されていますので、土鍋などの比較的浅めの鍋に食べやすく切った食材と汁を入れて火にかけ、食材に火が通れば出来上がり、もしくは"鍋奉行"と称する料理自慢のどなたかが、具材を入れる順番や、火の通り、食べるタイミングなどを指揮しながらも、ワイワイと楽しむスタイルなど、特に料理人でなくても誰でも簡単に楽しめるメニューとして定着しています。
とは言え、専門店で食べる鍋物は、やはり一味も二味も味わいが違いますが、何か違うのでしょうか?
重要なのは、食材にはそれぞれにうま味成分が含まれており、それらは水溶性で、単一よりもいくつかが混ざり合うことで、複雑で強いうま味に変化する、いわゆる「うま味の相乗効果」と言われる化学反応が起こることです。その化学反応は、約90℃前後(沸騰後、火を弱めて沸騰を押さえた状態)の水溶液=煮汁が20分前後ゆっくりと加熱されることで形成されます。次々に食材を投入して煮えたものから食べていく方式だと、煮汁の中で化学反応が起こるには時間が足りず、食材そのものを味わうことはできても、相乗効果によって数倍おいしくなった風味を味わうことはできません。一方、全部の食材を食べ終わったころ、鍋に残ったうま味が溶け出した煮汁には、時間の経過によって相乗効果が生まれています。〆の雑炊やうどんなどが一番おいしくなる理由はここにあります。ですが、それだと具材を食べた後にしか最終的なおいしさに辿り着けません。

そこを解決して専門店の味に近づけるポイントは、食材(主に野菜)を別々に下茹でし、アクを取って食べごろの一歩手前まで加熱したところで引き上げておくことです。盛り付け時に見栄えが良いように、巻きすなどで余分な水分を絞りながら形を整えておくと、お店の仕上がりにさらに近づきます。この手間で、食材が食べごろになる時間差を考えずに、土鍋に全食材を一気に、豪華に美しく盛り付けておくことができます。魚介類は酒を加えた湯で、表面だけにサッと火を通してアクと臭みを除いてから他の食材と一緒に盛り付ければ、土鍋の出汁が軽くわいた後、待ち時間なしでちょうど良い食感で食べることができます。
そして要の鍋汁は、食材を下茹でした後のそれぞれのゆで汁を捨てずにとっておき、まとめて鍋に入れ、そこへ昆布などを加えて15~20分加熱し、濾せば、鍋汁ベースの出来上がり。これに例えば、鶏鍋なら鶏ガラ、魚介なら魚のアラなどで取ったスープを煮詰めたものや、塩、醤油、味噌、その他の調味料を加えれば、うま味爆発!おいしい鍋汁の完成となります。後は、土鍋に盛り付けた食材にたっぷりの鍋汁を注いで加熱するだけです。
いかがですか?何でも煮てしまえば食べられる鍋も便利ですが、きちんと下処理をすることで、濁りなくコク深い奥行きのある風味を味わう鍋料理にも一度チャレンジしてみてください。うま味の相乗効果を実感できますよ!
ユーキャンではさまざまな食の講座をご用意しています。
ご興味のある方はぜひコチラへ→「ユーキャンの食関連講座のご案内」