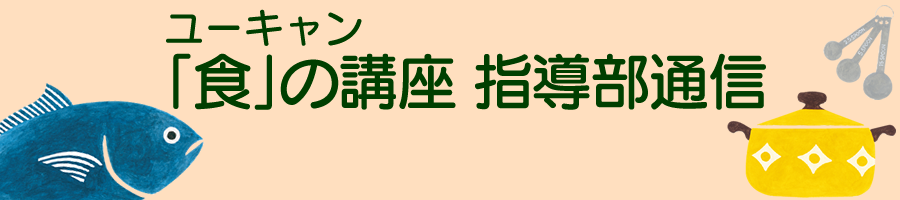2025年10月10日 北へ泳ぐ出世魚~ブリの現状と新しい食べ方~

「ブリ」と聞いて、何を思い浮かべますか?刺身、照り焼き、塩焼き、しゃぶしゃぶ──日本の食卓に欠かせない魚ですが、実は今、ブリの漁場が大きく変わりつつあります。
かつては富山湾の「ひみ寒ぶり」が冬の味覚の代名詞でしたが、近年では北海道沿岸での漁獲量が急増。その背景には、海水温の上昇による漁場の北上があります。北海道では30年前の約20倍ものブリが水揚げされ、今や全国トップクラスの漁獲量を誇ります。道南の八雲町や、せたな町などでは、定置網漁で大型の天然ブリが多く獲れ、地元のブランド化も進んでいます。富山湾の定置網で獲られ、氷見漁港で競られたブリのうち、重さや形などの基準を満たしたブリのみが「ひみ寒ぶり」を名乗れ、脂の乗りと身の締まりが特徴ですが、近年は海洋環境の変化により、漁獲時期や品質のばらつきも課題になってきています。対して北海道産は、回遊ルートの変化により大型魚が増え、脂の質も向上していると評価されています。

ブリは「出世魚」としても知られ、成長に応じて呼び名が変わるのは有名ですが、関東ではワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ、関西ではツバス→ハマチ→メジロ→ブリ。関西以西では縁起の良い魚として、おせち料理にも登場し、「出世」や「成長」を願う象徴として親しまれてきました。
歴史をたどると、戦国時代末期には富山湾で「ブリ台網漁」が行われており、江戸時代には藩の財政を支える重要な産業でもありました。明治以降は定置網漁法が発達し、昭和期には全国的に漁獲量が増加。1970年代には年間5〜6万トンに達するほどでした。現在では養殖技術も進化し、安定供給が可能になっていますが、天然物の価値は依然として高く、季節感や地域性を感じさせる食材として人気です。

皆さんの地方でも定番な食べ方があると思うのですが、折角ですから、定番料理以外でブリを楽しむアレンジメニューを少しご紹介しておきましょう。
●「ブリのカレー煮」(2人分)
<材料>ブリ切り身2切れ、玉ねぎ1/2個~1個、トマト1個、お好みでニンニク&生姜のみじん切り、カレー粉・しょうゆ・みりん各大さじ1
<作り方>玉ねぎとトマト(ニンニク&生姜)を炒め、ブリを加えて調味料と水100mlで煮込むだけです!15~20分ほどで完成です。
●「ブリのユッケ風」(1〜2人分)
<材料>刺身用ブリ100g、ごま油小さじ1、醤油小さじ1、卵黄1個、白ごま・刻みネギ少々
<作り方>ブリを細切りにし、調味料と和える。卵黄をのせて完成です!簡単でしょう!?

他には、低温(80℃程度)のオイルでじっくり火入れ。洋風前菜としてワインにも合う「ブリのコンフィ」や、加熱してほぐしたブリをクリームチーズと混ぜてペースト状に、パセリのみじん切りやタバスコを少々。クラッカーにのせて前菜に、などなど。
季節の変化とともに海を旅するブリ。次に食卓に並ぶブリは、どこから来たのか──そんな視点で味わってみるのも一興です。地域によって味わいが異なるブリを、ぜひ食べ比べてみてください。秋の食材が豊かになるこの季節、ブリの新しい魅力を発見するきっかけになれば幸いです。
ユーキャンでは食に関するさまざまな講座をご用意しています。詳しくはこちらから→「ユーキャン食関連講座のご案内」