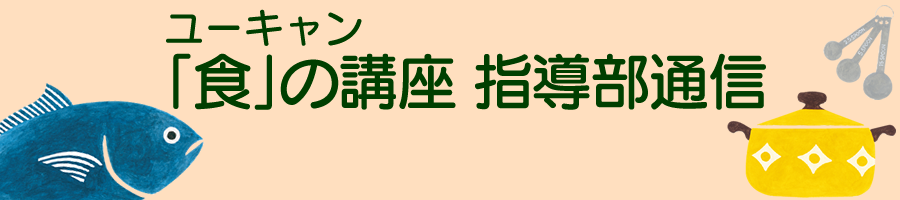2025年4月18日 今からはじめる5月病対策
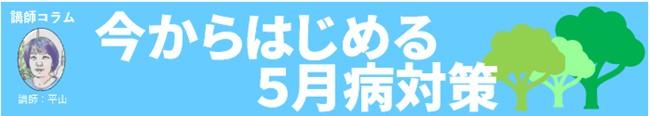
4月も中旬が過ぎました。新しい環境で緊張が続き、慣れとともに疲れも出てくる頃です。疲れやストレスが溜まると、心身ともに不調が起こることがあります。適度な運動と休息で、ストレスや疲れを解消していきましょう。

■「5月病」とは?
新年度がはじまる4月を経て、5月ごろになると、環境の変化や、勉強や仕事、責任などの新しい負担に対するストレスが原因で、心身に不調をきたすことがあります。一般的に、これを5月病と呼びますが、正式な病名ではありません。やる気が出ない、食欲がない、眠れないなどの初期症状のあと、徐々に体調を崩し、うつ病などの心の病に移行することもあります。
現代社会では、5月病に限らず、心の病にかかる人が増加していることから、メンタルヘルスケア(精神の健康を保つこと)が重要視されています。
■自分のストレスサインを知る
ストレスは少なからず誰にでもあるものですが、生活していくうえでストレスをゼロにすることはできません。ストレスとは上手くつきあっていくことが必要なのです。
そこで重要なのは、ストレスのセルフケアです。ストレスを感じると、眠れなくなる、お腹が痛くなる、イライラするなどの症状がでます。こうした症状に気づいたら、それはストレスを感じているサイン。自分のサインを知っておくと、すぐにストレスに気づき、早めに対処することができます。ストレスには、早めのセルフケアで、それ以上の悪化を防ぐことが大切です。
■セルフケアを身につける
セルフケアにはさまざまな方法があります。筋肉をゆっくり伸ばすストレッチングや適度な運動は、心身のリラックスに効果的です。ほかにも、親しい人たちとの交流や趣味を見つけるなど。テレビを見て笑ったり、映画をみて泣くといった行為も、ストレスを解消し、自律神経のバランスを整える効果があります。自分に合ったセルフケアでストレスを解消することが大切ですが、たばこやお酒に頼る方法は避けましょう。ストレス状態から逃げたい思いでたばこやお酒の量が増えると、体に悪影響を及ぼすばかりか、依存症となる場合もあるので注意しましょう。

■ストレスに強い心身を手に入れる
ストレスには、セルフケアで早めに対処することが重要ですが、まずはストレスに強い心身づくりを目指しましょう。心身の健康は、整った生活習慣から。「食事」「運動」「睡眠(休養)」の3つを整えることからはじめてみましょう。
「食事」は、栄養のバランスを考えて、規則正しい時間に食べることが大切です。栄養のバランスは、1食や1日あたりで考えるのではなく、「今日は野菜が少なかったから、明日は多く摂り入れよう」や「昨日は肉料理だったので、今日は魚料理を選ぼう」のように、1週間あたりでおおまかに捉えると継続しやすくなります。また、体をつくるたんぱく質、疲労を回復するビタミンB1、カルシウムの吸収をUPするビタミンDなどは積極的に摂取したい栄養素です。ストレスがかかると、ビタミンCが大量に消費されるので、ビタミンCも忘れずに!
「運動」が毎日できれば理想的ですが、難しい場合は、ひと駅歩く、エレベーターを使わずに階段で上る、動画を見ながらストレッチをするなど、スキマ時間を利用してちょこちょこ運動を取り入れてみましょう。
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」によると、成人の適正な睡眠時間には個人差があるものの、6時間以上を目安に確保することを推奨しています。適正な睡眠をとるためには、日中、日光に当たって体内時計を整える、適度な運動、入浴で体を温める、就寝直前の夜食を控えるなど。
ストレスによるメンタル不調は誰にでも起こることです。ストレスのセルフケアの知識、方法を身につけ、心身ともに健康に過ごしましょう。

ユーキャンでは、「調理師講座」や「食生活アドバイザー(2・3級)合格指導講座」、「食育実践プランナー」、「離乳食・幼児食コーディネーター講座」、「発酵食品ソムリエ講座」、「スポーツ栄養プランナー講座」などなど、多彩な講座をご用意しています。
まだ「新しい学び」を発見していない方、もっと学びを増やしたい方は、ぜひコチラをご覧ください→「ユーキャンの食関連講座のご案内」